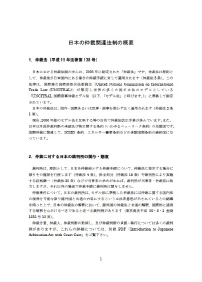Overview of Arbitration Related Legal System in Japan
日本の仲裁関連法概要
1.仲裁法(平成15 年法律第138 号)
日本における仲裁法制の中心は、2003 年に制定された「仲裁法」です。仲裁法は原則として、仲裁地が日本国内にある場合の仲裁手続に対して適用されます(仲裁法3条)。この法律は、国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL))が策定し世界の多くの国が立法のモデルとしている「UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法(以下、「モデル法」と呼びます。)」に準拠して制定されています。
日本の仲裁法は、国内・国際あるいは民事・商事を問わず広く適用されます(仲裁法2 条1 項)。
なお、2006 年版のモデル法を反映する等の目的で仲裁法改正が2023年に行われました(2024年4月1日施行)。また、日本は外国仲裁判断の承認及び執行関する条約(いわゆるニューヨーク条約)の加盟国です。国際仲裁に関連して、ICSID 条約、エネルギー憲章条約などの多数国間条約の締約国になっています。
2.仲裁に対する日本の裁判所の関与・態度
裁判所は、原則として、日本を仲裁地とする仲裁手続について、仲裁法に規定する場合に限りその権限を行使します(仲裁法4 条)。保全処分(仲裁法15 条)や裁判所により実施する証拠調べ(仲裁法35 条)などで当事者の求めがあれば、裁判所が当事者・仲裁廷に助力しますが、それ以外の場面で仲裁手続に裁判所は関与しません。
仲裁事件について、日本の裁判所は、モデル法に準拠した仲裁法には仲裁に関する国内法の規律を可能な限り諸外国と共通の内容にするという立法者意思が示されているとの認識を持った上で、日本の仲裁法の解釈において、諸外国の仲裁法と共通の解釈、国際的に通用する解釈を心がけるべきであると述べる裁判例があります(東京高決平成30・8・1 金商1551 号13 頁)。
仲裁合意、仲裁人、仲裁判断の取消し、及び仲裁判断の承認・執行については多くの裁判例がありますが、これらの詳細については、別紙PDF「日本の仲裁法に関する裁判所の裁判例の概説(Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Case)」をご覧下さい。
3.仲裁代理・仲裁人法制
日本においては、「弁護士法」により、日本の裁判所における代理権は日本の弁護士に限定されていますが、日本を審問場所とする国際仲裁手続における代理権については、外国弁護士にも広く開放されています。
具体的に説明しますと、日本では、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(昭和61年法律第66号)が、外国弁護士による日本国内での法律事務の取扱いについて定めています。同法の下で、次の①又は②に該当する外国弁護士は、日本において国際仲裁事件の手続を代理することができます。
① 法務大臣の承認及び日本弁護士連合会の名簿登録を受けた「外国法事務弁護士」の資格を有する者(外弁法5 条の3)
② ①以外の外国弁護士で、外国においてその資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者であって、当該仲裁事件をその外国において依頼され又は受任した者(外弁法58 条の2)
また、一般的に、仲裁法に基づく適正な手続により行われる仲裁事件については、外国弁護士など日本の弁護士以外の者であっても仲裁人としての活動をすることが認められており、実際にも、日本の弁護士以外の者による仲裁人としての活動が広く行われています。
日本の仲裁法に関する
裁判所の裁判例の概説
Introduction to Japanese Arbitration Act with Court Cases